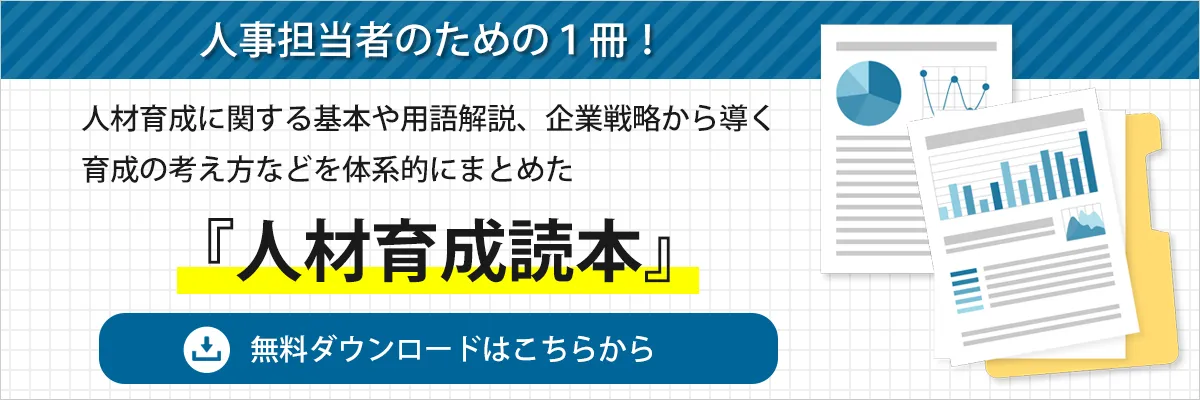eラーニングで行う社員研修│メリットや集合研修との違いは?
従業員のスキルアップのために、現状の社内研修制度を見直すなら、eラーニングの導入を検討するのがおすすめです。eラーニングとは、インターネットを利用した学習形態のことで、新たな社員研修の実施方法として注目されています。インターネット環境とパソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末を用意するだけで、受講者は時間や場所を選ばず柔軟に学習が可能です。
この記事では、社員研修をeラーニングで行う方法について解説します。従来の集合研修との違いや、eラーニングのメリット、活用方法などをご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
社員研修におけるeラーニングと集合研修の違い
従来の企業の社員教育では、集合研修が主流でした。eラーニングで社員研修を実施する場合、集合研修とはどのような違いがあるのでしょうか。まずは、基礎知識としてそれぞれの研修方法の特徴をご説明します。
eラーニングの特徴
eラーニングは、学習者の端末でインターネットにアクセスして、専用の学習管理システム(LMS)上で行われます。学習教材を使用して個人で受講する仕組みのため、時間や場所を問わずに学べるという特徴があります。一方で、講師や他の受講者とのコミュニケーションは発生しません。
集合研修の特徴
集合研修は、事前に指定された日時に研修会場で開催されます。講師と受講者が会場で対面し、リアルタイムで指導を受ける方法です。コミュニケーションを取りやすく、複数人で学習するため、適度な緊張感があります。その場で講師に質問したり、参加者同士で話し合ったりすることが可能です。
eラーニングで対応可能な社員研修の内容
eラーニングで企業研修を実施する場合は、以下のような幅広い領域の学習に対応可能です。自社の人材育成の目的に合わせて、eラーニングによる社員研修を検討してみてはいかがでしょうか。
eラーニングのみで対応可能な研修の領域
eラーニングは基本的に、体系的な知識の習得や情報共有を軸とする研修に向いています。eラーニングのみで完結できるのは、座学で読む・見る・書くといった勉強方法に取り組むような講義型の研修です。多くのeラーニングサービスでは、動画教材が充実している傾向にあります。たとえば、わかりやすいアニメーション形式のコンテンツで理解を促し、学習効果を高めるよう工夫された教材もあります。
一方、動的な学習が必要なケースは、一般的にeラーニングに適さないとされています。具体的には、グループディスカッションやグループワークのほか、実技・体験を伴う研修は対面で実施することが多くなるでしょう。ただし、eラーニングの研修コンテンツの中には、疑似体験により動的な学習をサポートできるものもあります。実践的な学びの場面では、こうした研修コンテンツを活用するのも有効です。
例えば、NTT HumanEXの「防災インバスケット」は、被災時の現場マネジメントをオンライン上で疑似体験しながら学べるeラーニングのプログラムです。リーダー層が初動対応・意思決定・優先順位設定などのスキルを身につけることで、被災時の実践的な対応力の向上を期待できます。
防災インバスケット 災害時の現場マネジメントをオンライン上で“疑似体験”!
URL:https://www.ntthumanex.co.jp/service/binbasket/
eラーニングで行う主な研修の種類
新入社員向け研修
新入社員研修は、新入社員や内定者を対象に行われる基礎研修です。社会人として仕事をするうえで必要な基本のビジネススキルを身につけさせる 目的があります。主な研修テーマは「ビジネスマナー」「社会人としての心構え」「文章の書き方」「オフィスソフトの使い方」などです。
中堅社員向け研修
中堅社員向け研修は、将来のリーダー候補として活躍する中堅社員を対象に行われる研修です。若手社員を指導し、管理職を補佐する立場にある中堅社員のさらなる成長を促す目的があります。主な研修テーマは「リーダーシップ」「フォロワーシップ」「コミュニケーション」「課題解決」などです。
管理職向け研修
管理職向け研修は、マネジメント層を対象に行われる研修です。重要な判断を担い、組織を成長へ導くために欠かせない高度なスキルを習得させる目的があります。主な研修テーマは「リーダーシップ」「マネジメント」「目標管理」「人事評価」「リスク管理」などです。
全社員向け研修
企業内の全社員を対象に、適切な働き方に関する最新の知識を身につけさせる 研修です。法令遵守を目的とした「コンプライアンス研修」、ハラスメントの防止を目的とした「ハラスメント研修」、ストレスによる不調の理解と防止を目的とした「メンタルヘルス研修」などが挙げられます。
社員研修をeラーニングで行うメリット・デメリット
社員研修をeラーニングで実施すると、受講者側・企業側にそれぞれどのようなメリット・デメリットがもたらされるのでしょうか。人事部門のご担当者様は、ぜひ参考にしてみてください。
社員研修をeラーニングで行うメリット
受講者側のメリット
eラーニングの教材は繰り返し視聴できるので、一人ひとりの理解度や習熟度に合わせて履修できます。例えば「苦手な分野は重点的に学ぶ」といったように、受講者が自分に適した学習方法を選択でき、効果的な自律学習を実現可能です。
また、eラーニングの受講では時間や場所の指定がないので、いつでもどこでも研修を受けられます。受講者は業務のすき間時間を活用して、自分のタイミングで学習を進められます。コア業務で多忙な従業員も効率的に学習しやすいところが魅力です。また、テレワーク中の従業員への研修実施にも対応できます。
企業側のメリット
企業がeラーニングシステムを導入すると、学習成果をデータ管理しやすくなります。システムの管理機能を活用すれば、受講者ごとの進捗を一元管理して、全体の学習状況の把握が可能です。また、システム上で教材の修正を一括で行えるので、教育担当者の業務負担を大幅に軽減できるでしょう。
さらに、eラーニングは集合研修と比較して研修にかかるさまざまなコストの削減が期待できます。例えば、研修会場を確保する費用や、配布資料を紙で作成する手間、講師を手配する費用などが不要となります。集合研修を実施するコストが課題となっている場合は、eラーニングを活用すると良いでしょう。
社員研修をeラーニングで行うデメリット
受講者側のデメリット
受講者が手を動かす実技の分野では、基本的にeラーニングよりも講師から対面で直接指導を受けるのが望ましいでしょう。前述した通り、eラーニングは一般的に動的な学習には適さないとされています。なかには疑似体験が可能な研修コンテンツもあるものの、学ぶ領域によってはeラーニングのみでは技術の習得が難しい可能性があります。
企業側のデメリット
企業側のeラーニングのデメリットとして、受講の強制力が低い点が挙げられます。受講管理を徹底し、万が一遅延が発生した場合はこまめに受講者をフォローする仕組みが必要です。また、個人で学習する際はモチベーションの維持が難しいので、学習意欲を保つための工夫も欠かせません。このほかに、受講にあたってITの基礎知識が必須となり、環境整備が必要になることにも注意しましょう。
社員研修に使うeラーニングシステムの主な種類
eラーニングシステムは、大きく「自社教材型」「汎用型」「特化型」の種類に分けられます。ここでは、社員研修に使うeラーニングシステムの主な種類と、それぞれの特徴をご紹介します。
自社教材型
自社教材型は、システム上で自社オリジナルの教材を作成し、管理できるタイプのeラーニングシステムです。システムの機能を使ってオリジナル教材やオリジナルコースを自由に作れるので、自社独自のマニュアルで社員教育を行えます。なお、自社で教材を作成するだけでなく、外部の専門業者に教材制作を外注することも可能です。
汎用型
汎用型は、基礎的なスキルの習得に適したコンテンツを幅広く備えたeラーニングシステムです。業界や業種を問わず、あらゆる法人向けの教材が用意されています。例えば、どんな企業においても重視される「コンプライアンス」や「個人情報保護」といった汎用的なテーマのコンテンツが網羅されているのが特徴です。多種多様なコンテンツの中から、自社の教育施策に必要なテーマを選択できます。既存の教材を使用するので、教材を作成する工数がかかりません。教材作成の内製化が難しい企業にもおすすめできます。
特化型
特化型は、特定の専門分野に焦点を当ててコンテンツを提供するeラーニングシステムです。専門知識や専門技術を取得するために、目的別に専門性の高いコンテンツが用意されています。例えば、「ITスキル」「情報セキュリティ」「医療」「介護」といった分野が挙げられるでしょう。専門性の高い社内教育を必要とする業界・業種の企業に適しています。
社員研修用のeラーニングシステムの選び方
eラーニングシステムを導入する際は、教材コンテンツの内容や必要な機能などを整理して、組織の要望に適したサービスを選定することが大切です。各社のeラーニングシステムの特徴をチェックして、自社に適したサービスを比較検討しましょう。
システムの違い
eラーニングシステムの提供形態は、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」に分けられます。なかでも近年は、インターネット経由でシステムを利用する仕組みのクラウド型が主流となっています。一方、オンプレミス型は社内でシステムの構築と運用を行う点が主な違いです。クラウド型では機器の購入・設置が不要なため、オンプレミス型と比べて初期費用やランニングコストを抑えられます。
コンテンツの豊富さ
各社のeラーニングシステムで提供される教材の種類や量を比較してみましょう。多彩なコンテンツが提供されているシステムなら、従業員が自分の業務と関連する教材を見つけやすく、持続的な学びを促せます。その際は、コンテンツの質にも着目することが大切です。「自社の目的に適したテーマのコンテンツがあるか」「コンテンツの内容がわかりやすく、業務に役立てられるか」といった観点でチェックしてみましょう。
独自コンテンツの制作機能
eラーニングシステムによっては、独自コンテンツを制作する機能が搭載されています。教材の制作やカスタマイズができるか確認しておくと良いでしょう。教材コンテンツを一から制作する以外にも、特定の事例を追加したり、自社で作成したコンテンツと併せて活用したりできると便利です。自社の目的に適したカリキュラムを柔軟に作成できるeラーニングシステムをおすすめします。
操作性
eラーニングシステムの操作性が悪いと、受講者のストレスにつながり、学習の進捗に影響を与えるおそれがあります。そのため、直感的に使えてスムーズに受講できるか、事前にシステムの操作性を確認しておきましょう。受講者側の操作性はもちろん、管理者側の操作性にも配慮する必要があります。教材コンテンツの管理や、学習履歴の確認がしやすく、業務効率化に役立つシステムを選びましょう。
コスト面
eラーニングシステムを導入する際は、初期費用や月額費用などの一定の料金が発生します。社員研修の予算の範囲内で、必要な機能が搭載されたシステムを選びましょう。利用料金やプラン内容はサービスによって異なるので、求める機能や組織の規模に応じて検討するのがポイントです。単に費用の安さで比較するのではなく、自社の社員教育の効果を高められるシステムを選定すると良いでしょう。
運用サポートの有無
eラーニングシステムのサービス提供会社がどのような運用サポートを提供しているか、あらかじめ確認しておくようおすすめします。例えば、導入前は機器の準備や運用体制の構築などの支援を受けられると良いでしょう。さらに、導入後は運用改善のアドバイスを受けられるようなサービス提供会社であれば、社内にシステムを定着させやすくなります。導入実績が豊富で、信頼できるサービス提供会社に依頼しましょう。
社員研修でeラーニングを上手く活用するポイント
社員研修でeラーニングを活用するには、以下のポイントを意識することが大切です。eラーニングを活用して研修効果を高め、導入を成功へ導くために、ぜひ参考にしてみてください。
内容によって、他の研修方法と適宜組み合わせる
階層別研修や職種別研修のような、単に知識を習得するのみでは不十分な場合は、eラーニングを他の研修方法と組み合わせると良いでしょう。eラーニングで体系的に知識を身につけた うえで、対面で実技を習ったり他の受講者と一緒に学んだりすることで、スキル向上が期待できます。あるいは、集合研修やセミナーを実施した際、予習・復習・テストにeラーニングを活用するというのも一つの方法です。
教材は適宜改善する
eラーニングの教材は定期的に見直しを行い、適宜改善することが大切です。受講率が低いコンテンツがある場合は、原因を特定して継続的に改善する必要があります。受講状況やテスト結果などを参考に、コンテンツのボリューム・テーマ設定・難易度などを調整すると良いでしょう。例えば、従業員が業務の合間でも受講しやすくなるよう、短時間で視聴できるコンテンツを提供するといった対策が挙げられます。
モチベーションを維持できるよう対策を行う
eラーニングは受講の強制力が低い傾向にあるので、学習のモチベーションを維持できるよう工夫する必要があります。管理者は部下の受講履歴を確認してフィードバックや支援を行うなど、社内でサポートを充実化させることが大切です。また、実務に即したケーススタディを導入すると、受講者がコンテンツの内容に興味を抱きやすくなります。主体性を持って学べるような対策を講じましょう。
eラーニングを活用して社員研修の学習成果向上をめざしましょう!
ここまで社員研修をeラーニングで行う方法をお伝えしました。eラーニングは、新人研修から管理職研修まで幅広い社員教育のニーズを満たせる教育手法です。コンプライアンス研修やハラスメント研修のようなテーマ別の講座にも対応可能で、効率的かつ効果的な研修を実現できます。
NTT HumanEXでは、豊富な分野から課題に合わせて選べるeラーニングの研修教材をご用意しています。受講者の“自分ごと化”を促進し、インプットとアウトプットを交えながら思考力を育む設計により、学びを深められるのが特長です。eラーニングの学習コンテンツをお探しのご担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。