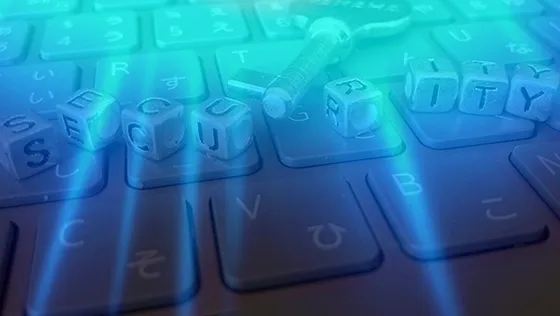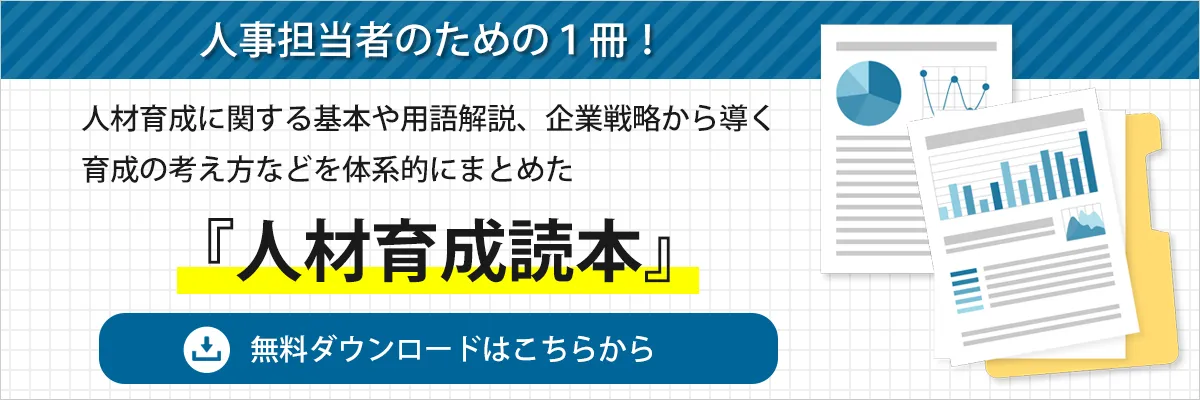eラーニングで行うハラスメント研修|テーマの種類と成功させるコツは?
社員教育では、従業員にビジネススキルを習得させることに加えて、コンプライアンスや倫理観を身につけさせることも重要です。特に、近年は多くの企業でハラスメントの相談が増加し、課題となっています。良好な職場環境を作るために、研修を通じてハラスメントのない職場を実現しましょう。
本記事では、eラーニングで行うハラスメント研修について解説します。ハラスメント研修で取り組むテーマの種類や、研修を成功に導くコツまでお伝えしますので、研修を担当している方はぜひ参考にしてみてください。
eラーニングとハラスメント研修
はじめに、「eラーニング」や「ハラスメント研修」に関する基礎知識を解説します。ハラスメントのない職場づくりへ向けて研修の導入を検討している人事労務を担当する方は、基本を改めて確認してみましょう。
eラーニングとは
eラーニングとは、インターネットを利用した学習形態を指します。受講者がパソコン・スマートフォン・タブレットなどを用いて、自分のペースで学習コンテンツを視聴して学べるという特徴があります。研修を実施する際は、専用のeラーニングシステムを使用することが一般的です。なお、eラーニングシステムは「学習管理システム(LMS)」とも呼ばれます。
ハラスメント研修とは
ハラスメント研修とは、職場におけるハラスメントの基本的な考え方を学ぶとともに、防止につなげる研修のことです。厚生労働省では、以下の3つの要素を全て満たすものを「ハラスメント」として定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
また、ここでいう「職場」とは労働者が業務を遂行する場所を指し、自社のオフィスだけでなく、取引先や通勤中なども含まれます。そのため、勤務時間外に開催される宴会のような場面も、実質上は職務の延長であることから、「職場」と見なされる可能性があるでしょう。なお、「パワーハラスメント」や「セクシャルハラスメント」をはじめとした、具体的なハラスメントの種類については、後の研修テーマの見出しで詳しく解説します。
ハラスメント研修では、ハラスメントに対する従業員の理解を促すとともに、予防策や対処法などを学ばせます。管理職を含む、全社員が研修の対象者です。
【出典】厚生労働省 あかるい職場応援団「ハラスメント基本情報 ハラスメントの定義」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
なお、ハラスメントについては以下の記事もご参照ください。
「ハラスメント教育とは何か」 https://www.ntthumanex.co.jp/column/harassment/
eラーニングで行うハラスメント研修とは
近年は、さまざまな研修形式の中でも、eラーニングの形式でハラスメント研修を実施するケースが多くなっています。
eラーニングでは、職場で発生する可能性があるハラスメントの基礎知識のほか、「ハラスメントの事例」「ハラスメントが発生した場合の対処方法」「ハラスメントが組織に及ぼす影響」「ハラスメント防止対策」などを動画やテキストで学びます。
ハラスメント研修は、eラーニング以外に社内研修・外部研修・オンライン研修(ライブ型)などの形式があります。なかでもeラーニングは、全従業員が対象となるハラスメント研修に適した形式です。研修の運営工数が削減され、効率化が期待できます。
ハラスメント研修が重要な理由
ハラスメント研修は、ハラスメントの発生を未然に防ぐ目的で実施されます。研修が重視される背景として、ビジネスシーンにおけるハラスメントの相談件数の多さが挙げられます。
厚生労働省が令和5年度に実施した職場のハラスメント相談に関する調査によると、過去3年間に「ハラスメントに関する相談がある」と回答した企業の割合は、パワハラの相談で64.2%、セクハラの相談で39.5%となりました。また、従業員数1,000人以上規模の企業では、過去3年間に「相談件数が増加している」と回答した企業の割合のほうが、「相談件数は減少している」と回答した企業の割合よりも高くなっています。
近年は、依然として多くの企業がハラスメントの防止策を講じる必要性が高まっている状況です。ここでは、ハラスメント研修が重要な理由をご紹介します。
【出典】厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」P.33 https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001256082.pdf
「ハラスメント防止の義務化」に対処するため
2020年6月1日から改正「労働施策総合推進法」が施行され、事業主がパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されました。さらに2022年4月1日以降は、中小企業の事業主にもパワーハラスメント防止措置が義務づけられています。組織の規模を問わず、全ての企業でハラスメント対策が求められています。
【出典】厚生労働省「パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
優秀な人材の流出を防ぐため
ハラスメントによって職場環境が悪化すると、優秀な人材の離職が懸念されます。職場で発生したハラスメントの問題を放置すると、従業員の求職や退職が増加するおそれがあるでしょう。人材確保の観点からも、ハラスメント対策は重要だといえます。
取引先や顧客との良好な関係を築くため
自社内で日常的にハラスメントが横行している場合、自社の社員が取引先や顧客に対して不適切な言動を行ってしまう可能性があります。顧客や取引先からの信頼を失うリスクを避けるためにも、ハラスメント研修を徹底することが大切です。
職場の安全を守るため
ハラスメントは被害者に対する人権侵害と見なされ、職場の安全を守る観点からも発生を防止する必要があります。過去にはハラスメントが原因で訴訟につながった事例も数多く存在します。なかにはパワハラをした人だけでなく、企業に責任が認められた裁判例もあるため注意が必要です。
【出典】厚生労働省「ハラスメント基本情報 裁判例を見てみよう」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/
eラーニングで行うハラスメント研修のテーマの種類
ハラスメント研修をeラーニングで実施する企業が多くなっています。ここでは、eラーニングで行うハラスメント研修を、テーマ別にご紹介します。
パワーハラスメント(パワハラ)
「パワーハラスメント(パワハラ)」とは、職場内での優越的な立場を利用して、過度な叱責やいじめを行うことを指します。なかでも上司(管理職)が部下に対して行うパワハラがよく知られています。マネジメント層・管理職向けの研修では、パワハラに該当する言動を学び、自身の認識とすり合わせることで適切な接し方を身につけさせることが重要です。
「事例から学ぶパワーハラスメント ~働きやすい職場を考える~」 https://www.ntthumanex.co.jp/service/harassment/
セクシャルハラスメント(セクハラ)
「セクシャルハラスメント(セクシュアルハラスメント、セクハラ)」とは、相手の意に反した性的な言動で不利益を与えたり、就業環境を害したりすることです。男性・女性間だけでなく、同性間や性的少数者に対するものも含まれます。場合によっては法的なトラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。研修では、性に関する不適切な言動や差別について学び、セクハラを横行させない環境づくりにつなげます。
モラルハラスメント(モラハラ)
「モラルハラスメント(モラハラ)」とは、道徳や倫理に反した嫌がらせにより、言葉や態度で相手に精神的な苦痛を与えることです。具体的には、「無視をする」「仲間外れにする」「業務妨害をする」「プライベートに過干渉する」などの言動が挙げられます。職場の上下関係にかかわらず起こり、表面化しづらく加害者が自覚しづらいため、研修ではモラハラの定義や具体例について学びます。
マタニティハラスメント(マタハラ)
「マタニティハラスメント(マタハラ)」とは、女性従業員が妊娠・出産・育児に関して嫌がらせや不当な扱いを行うことです。大きく「産休・育休などの制度を利用したことに対するハラスメント」と「妊娠や出産をした状態に対するハラスメント」の2種類に分けられます。研修では、仕事と育児を両立する社員への理解を促すことで、ハラスメント防止につなげます。
パタニティーハラスメント(パタハラ)
「パタニティーハラスメント(パタハラ)」とは、男性従業員の育児休暇(育児休業)の利用を阻害したり、制度利用を理由に嫌がらせをしたりすることです。具体的には「育休の申請を認めない」「復職後に仕事を与えない」などが挙げられます。研修では、マタニティハラスメントと同様に仕事と育児を両立する社員を守るために、ハラスメント防止の考え方を周知します。
ケアハラスメント(ケアハラ)
「ケアハラスメント(ケアハラ)」とは、仕事と介護を両立する従業員に対して、介護休暇の利用を阻害したり、制度利用を理由に嫌がらせをしたりすることです。社会の少子高齢化にともない、今後は介護に携わる働き手が多くなると考えられています。ハラスメント研修によって、多様な働き方への理解を促すことが可能です。
アルコールハラスメント(アルハラ)
「アルコールハラスメント(アルハラ)」とは、飲酒にまつわる嫌がらせをすることです。場合によっては命にかかわる危険性があります。具体的には「飲酒の強要」「イッキ飲ませ」「意図的な酔いつぶし」などが挙げられます。研修を通じて、勤務時間外に起こり得るハラスメントについても問題意識を持たせることが可能です。
SOGIハラスメント
「SOGI(ソジ)ハラスメント」とは、性的指向・性自認にまつわる嫌がらせや不当な扱いを行うことです。性的指向・性自認にまつわる差別的な言動や、第三者の性的指向・性自認を許可なく公表する「アウティング」などが該当します。研修によって、ジェンダーに関する多様性への理解を促し、良好な職場環境を作ります。
レイシャルハラスメント(レイハラ)
「レイシャルハラスメント(レイハラ)」とは、人種・民族・国籍にまつわる嫌がらせや不当な扱いを行うことです。近年はビジネスシーンのグローバル化を背景に、外資系企業に限らず外国人労働者と同じ職場で働くケースが多くなっています。研修の実施により、無意識の偏見や差別によるハラスメントの防止につなげます。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客・取引先が従業員に対して過度な要求を行い、業務を阻害することです。要求の妥当性にかかわらず、社会通念上不相当な言動はカスハラと見なされ、一般的なクレームとは区別されます。研修を通じてカスハラについて学ぶことで、従業員をハラスメントの被害から守ることが可能です。
ここまでご紹介したハラスメント以外にも、「スメルハラスメント」「ソーシャルメディアハラスメント」「リモートハラスメント」などのさまざまなハラスメントが懸念されています。上司・部下・同僚のほか、取引先や顧客との間でもハラスメントが発生する可能性があります。研修では最新のトレンドを踏まえて、多様なハラスメントについて学ぶことが重要です。
なお、NTT HumanEXでは、従来のハラスメントだけでなく、レイハラやSOGIハラなどの比較的新しいハラスメントまで網羅し、具体的なケースで学べるeラーニングを用意しています。ぜひ導入をご検討ください。
「コンプライアンスイマジン」 https://www.ntthumanex.co.jp/service/compliance-imagine/
eラーニングでハラスメント研修を行うメリット
ハラスメント研修をeラーニングで行うと、以下のさまざまなメリットが期待できます。自社のニーズに合わせて、オンラインでハラスメント研修を実施してはいかがでしょうか。
テストで理解度をチェックしやすい
eラーニングは受講中や修了後のタイミングで確認テストを実施できます。重要な知識の定着度や、研修内容の習熟度をチェックしやすいのがメリットです。一人ひとりの理解度が明らかになると、苦手分野を重点的に復習するといった効率的な学習を実現できます。
受講者の進捗状況を管理しやすい
管理職は、eラーニングシステムの受講管理機能やレポート機能によって、受講者の学習履歴や成績などを確認できます。全体の受講状況をリアルタイムで把握することが可能です。また、学習コンテンツを視聴開始していない受講者に対して、通知やアラートで受講を促すこともできます。
均一な教育の提供が可能になりやすい
eラーニングでは、受講者全員が同じ学習教材を使用するため、教育の質を均一に保ちやすくなります。たとえば、動画講座では講師の指導方法や能力により研修内容にムラが生じる心配がありません。また、多くの動画教材は受講期間内に視聴し放題になるので、全社的に知識の定着を図れます。
研修内容を更新しやすい
eラーニングは研修内容の管理が容易なため、最新の法律やガイドラインに即して学習コンテンツを更新できます。社会情勢やハラスメントに対する認識は時代とともに変化しやすいため、ハラスメント研修には最新情報を反映しやすいeラーニングが適しているといえるでしょう。
受講者が自分のペースで受講できる
eラーニングは受講者が1人で学習を進められるため、仕事の忙しさなど個人の都合に合わせて受講できる点がメリットです。特定の日時や場所が決められてしまう集合研修よりも受講しやすいので、期日を決めて従業員全員に受講させることができます。
eラーニングでハラスメント研修を行う際の注意点
eラーニングでハラスメント研修を行う際は、以下のポイントに注意しておきましょう。効果的に研修を実施するために押さえておきたい注意点をお伝えします。
モチベーションを維持してもらう工夫が必要
eラーニングによる学習は全般的に、進捗や成果が個人のモチベーションに左右されやすいのが注意点です。なかには個人学習で集中力が長続きしない受講者もいるでしょう。また、受講に強制力がないため学習が後回しになってしまうケースも珍しくありません。モチベーションを維持するための工夫が求められます。
集合研修が別途必要になる場合がある
eラーニングでは、基本的に講師や他の受講者とのコミュニケーションが発生しません。そのため、講師に質問してその場で疑問を解決したり、受講者同士の交流で切磋琢磨したりしにくいことが注意点です。また、実技をともなう研修内容の場合は、eラーニングのみで学習を完結するのが難しいケースもあるでしょう。
こうした注意点を踏まえて、「ブレンディッドラーニング」によって研修をカスタマイズする方法もおすすめです。ブレンディッドラーニングとは、複数の形式を組み合わせた研修方法です。必要に応じて集合研修やオンライン研修(ライブ型)を実施するといったように、eラーニングとの併用を検討してみましょう。
eラーニングでのハラスメント研修を成功させるコツ
eラーニングでのハラスメント研修を成功へ導くには、研修の設計や準備で以下の工夫をするとよいでしょう。ハラスメントのない職場づくりを実現するために、ぜひ参考にしてください。
目的を明確にする
ハラスメント研修を通じて、従業員の意識や行動を変化させる必要があります。そのためにも、事前に明確な目的を定めた上で研修を実施することが重要です。役職に関係なく、組織の全員がハラスメントについて適切に理解し、ハラスメントの予防や職場環境の改善に取り組む状態をめざしましょう。
適切な学習環境を構築する
ハラスメント研修は、従業員が学習内容を「自分ごと化」できないと十分な効果を期待しにくいといえます。特に、eラーニングで研修を実施する場合は、座学に加えてグループワークや講師への質疑応答の場を追加で設けるなど、受講者の積極的な参加を促すことが大切です。
ハラスメントを組織全体の問題と捉える
社内でハラスメントを横行させないためにも、一人ひとりがハラスメントを「個人の問題」ではなく「組織の問題」として捉える必要があります。研修では組織でハラスメントが発生する原因を学ぶとともに、受講者自身が問題点や改善策を考えることで、職場へ働きかける力を強化できると理想的です。
ハラスメントを許さない組織風土を醸成する
ハラスメント研修の実施と併せて、経営者から全従業員へ向けて明確な意思表示を行い、ハラスメントを許さない組織風土を醸成しましょう。経営者自身が研修を受講したり、ハラスメント防止へ向けて率先して行動したりすることで、従業員に対して強いメッセージを発信できます。
一度だけでなく継続的に行う
たった一度の研修で従業員の行動や意識を変化させ、定着させることは難しいといえます。そのため、ハラスメント対策研修は定期的に実施するのが望ましいでしょう。繰り返し継続的に研修を行うことで、従業員の行動や意識の定着化を推進しやすくなります。
eラーニングのハラスメント研修で職場環境の改善を目指しましょう!
ここまで、eラーニングで行うハラスメント研修について解説しました。ハラスメント防止へ向けて、多くの企業でeラーニングを活用した研修が実施されています。企業研修を担当している方は、eラーニングの研修シリーズが充実したNTT HumanEXへご相談ください。
NTT HumanEXでは、社員のエンゲージメント向上を支援する研修・eラーニングのコースをご用意しています。ハラスメント防止を目的とする企業さまには、「コンプライアンスイマジン」の体験型eラーニングがおすすめです。この学習コンテンツでは、パワハラやセクハラだけでなく、SOGIハラやレイハラなどの比較的新しいハラスメントについて具体的な事例から学ぶことができます。当事者の感情にもフォーカスしており、受講者が想像力をはたらせながら学習を進めていく実践的なコンテンツとなっています。
学習コンテンツの利用料金は、利用人数に応じて1ライセンスごとに発生する仕組みで、利用期間は3か月です。無料トライアルや無料の資料ダウンロードもご用意しているため、サービスの詳細をご希望の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
「社員のエンゲージメント向上を支援するNTT HumanEX サービス一覧」 https://www.ntthumanex.co.jp/service/